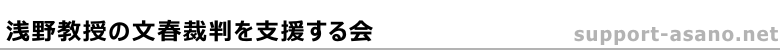9月27日に暗黒裁判の首謀者、冨田安信・前研究科長を証人尋問
原告・浅野教授も証言――地位確認訴訟第13回弁論で決定(下)
内田博文九大名誉教授が浅野教授の業績で陳述書
ハンセン病問題で最近も活躍し、『刑法と戦争 戦時治安法制のつくり方』(みすず書房、2015年11月)を出版している九州大学名誉教授・神戸学院大学法学部教授の内田博文さんが「浅野健一教授の教員業績に関する陳述書」(2016年4月20日)を京都地裁へ提出してくれました。
内田教授は刑事法の教育・研究に従事する他の者と同様、マスコミの犯罪報道について深い関心を持っており、浅野教授の活動、とりわけ、その著書『犯罪報道の犯罪』(学陽書房、1984年)に注目してきました。内田教授は1995年度に、当時在籍していた九州大学法学部及び大学院法学研究科に浅野教授を非常勤講師として招き、「刑法特殊講義」と「情報法制論」で講義を依頼しています。
内田教授は浅野教授が1994年から同志社大学大学院で教授として、実績を重ね、1998年に大学院文学研究科新聞学専攻(現在の社会学研究科メディア学専攻)に博士後期課程が増設された際、博士後期課程の「メディア・ジャーナリズム」コース長の教授に任用され、文部省(当時)より「Dマル合」教員(博士論文指導を担当し、主査として審査できる教員)の認定を受けたことを指摘しています。
〔浅野教授の場合、共同通信社記者としての経験を生かして、とりわけ「犯罪報道」のあり方について、多数の著書の刊行などを通じて、社会的注目を集める問題提起を行ったことなどが高く評価され、博士号取得と同等の業績があるとして、「研究指導教員」(「マル合教員」)の資格要件を満たしていると判定されたものと思われる。
同文学研究科博士後期課程(新聞学専攻)教授としての教育業績については、同志社大学法学部教員が作成した資料などによって、次のように指摘されている。
〈同社会学研究科メディア学専攻博士後期課程では、文学研究科新聞学後期博士専攻として設立(1998年)以来、2013年11月までの間に、8名が「新聞学博士」「メディア学博士号」の課程博士号を取得している。このうち、浅野教授が指導教授として専攻全体で博士課程を修了し、浅野教授が主査となって課程博士号を取得したのは4名に上る。文学研究科新聞学後期博士課程の時に、河崎吉紀(2003年博士号(新聞学)、現同志社大学社会学部メディア学科准教授、学部時代から浅野ゼミ)、韓景芳(2006年博士号(新聞学)、現・中国華東政法大学文学部新聞学専攻副教授)の各氏で、いずれも研究者として、国内外で活躍している。また、社会学研究科メディア学専攻博士後期課程になって以降、李其珍(2010年博士号(メディア学)取得、現・チョンガン大学コンテンツ専攻嘱託講師、韓国Imageframe, Inc.(図書出版キルチャッキ)編集長)、森類臣(2013年博士号(メディア学)取得、現・立命館大学コリア研究センター専任研究員)の2名が課程博士号を取得した〉
その他、博士号を取得はしていないが、浅野教授は4名の指導教授として博士論文の指導を行っている。この4名の中には、フランスからの日本政府国費留学生、インドネシア文部省奨学金留学生、日本学術振興会「DC2」特別研究員・2014年度内定者が含まれている。この指導実績は、他教授のそれと比較しても遜色がないものである。(略)
浅野教授が論文指導し、主査となって博士号を授与した院生は、文学研究科新聞学専攻と社会学研究科新聞学専攻・メディア学専攻の両方にまたがっており、4人のうち2人が文学研究科、2人が社会学研究科で取得している。博士の名称も、前者は「博士(新聞学)」、後者は「博士(メディア学)となっている。浅野教授が主査として博士号を授与したのが、「博士(新聞学)」も合わせると計4人であることは、社会学研究科事務室がまとめた社会学研究科(文学研究科時代を含む)発表のリストでも明らかである。〕
〔 同志社大学では、65歳が定年だが、大学院を担当している教員に限って、70歳まで一年毎に審議の上で定年が延長される「定年延長」制度がある。同大学では、自ら定年延長を希望しない教員を除いては、ほぼ全ての対象者が、形式的な手続きの上で、定年延長が認められてきたといわれている。しかし、浅野教授については、定年延長が認められず、2014年3月末日を以て、定年退職とされることになった。
この件に関して、浅野教授は、2014年2月3日、京都地方裁判所に対し、地位確認請求訴訟を既に提起している。定年延長を認めなかった大学の決定が裁量権を逸脱した不合理なものであるか否かが、同訴訟では争点になるものと思われる。
この点は本陳述書の範囲を越える問題であり、軽々に論じることは控えたいが、次の点だけは指摘しておきたい。もし、かりに上の大学の決定が浅野教授の教員業績、研究業績、教育業績等を理由とするものであるとすれば、その判断は適切なものではないという点がその第1である。それは上述したような浅野教授の業績からも明らかであろう。
第2は、浅野教授がその研究活動や教育活動に当たって、やや「過激な表現」を用いられ、既成の大学人から見て「違和感」が生じたとしても、そのことは定年延長の判断に当たって重要視されるべき事柄ではないという点である。それは元新聞記者という経験に基づく浅野教授に一流の表現方法ともいうべきものであって、この元新聞記者という経験に基づく研究、教育を期待して同志社大学は浅野教授を、それも大学院教授として招聘しているからである。やや「過激な表現」は浅野教授の一貫した表現方法であって、『犯罪報道の犯罪』などでも見られるところのものである。この『犯罪報道の犯罪』などの業績を高く評価して、同志社大学は浅野教授を招聘しているのである。にもかかわらず、定年延長の判断に当たって、それを重要なマイナス要因とすることは自己矛盾だと言わざるを得ない。この自己矛盾も裁量権の範囲内だということはできない。
第3は、浅野教授が学外での社会的な活動に忙殺される中で、勤務上、定期試験の監督を務められなかったなど、「穴をあける」ことが、かりに多少あったとしても、そのことは定年延長の判断に当たってことさらに重要視されるべき事柄ではないという点である。今日では、大学教員に対して、社会貢献活動が強く求められており、いずれも教員も教育活動と社会貢献活動の調整に頭を悩ましているからである。調整がうまく行かないこともあり得るのである。かりに、この点に問題があるとすれば、手続的正義を満たすという観点から、必要な手続を踏んで、抗弁などを聞いた上で、注意喚起の方法などにより、然るべき改善方を求めるべきであって、これらの手続を一切、取らずに、定年延長を拒否する理由とすることは相当ではなかろう。 〕
内田教授の陳述書は、浅野教授の教育研究がメディア学だけでなく、法学の分野でも高く評価されており、被告側の冨田氏と同僚4人の「不良教授論」を一蹴しています。
弁護団が今後の方針を説明
口頭弁論が終わった後、裁判所内の待ち合わせ室で、報告会がありました。傍聴者が自己紹介した後、代理人弁護士4人を代表して武村弁護士が「同志社大学では、大学院教授は特段の事由がない限り、70歳まで定年が延長されてきた。定年延長は、雇用の継続であり、再雇用ではない。特に浅野教授が所属する社会学研究科(旧文学研究科)においては、希望する院教授を辞めさせた前例はない。最近は、それは、短期の1年契約を繰り返してずっと働かせてきた非正規労働者を、相応の理由がないのに契約を打ち切るのに正当性がないという判決が出ている。浅野教授は20年間も大学院教授を務めており、研究科委員会で否決したのは不当だ。我々は、被告側が提出した「1975年以降に70歳をまたずに退職した院教授58人」の一人ひとりの退職理由を調べたら、すべて自己都合だった。専攻や研究科の教授会で定年延長を拒否した例は一つもなかった。これからも、原告の支援をお願いしたい」と話した。
浅野教授は「庄司先生の証人が認められなかったのは残念だが、同大における定年延長の規定、実態は裁判官にこれまでの書面で分かったということだと思う。被告側の証人が冨田氏一人というのは理解できない。なぜなら、冨田氏は、学校法人同志社と私の労働契約に関して、まったく権限を持っていないからだ。彼が社会学研究科長として私にやった蛮行は追及できるが、同大の定年延長の仕組みと、私の権利について彼はまったくの素人だ。私の研究分野もまったく分からない。冨田氏と若い弁護士に丸投げしている学校法人同志社と同志社大学はあまりに無責任だ」と話しました。その上で、冨田氏は、ウソを連発して、自身の暴挙を正当化すると思う。傍聴席を埋め尽くして、彼の偽証を監視してほしい」と呼び掛けました。
大学のある支援者はこう述べました。
〔 70歳までに退職する院教授は20数%いるという被告の主張は、原告側の調査で完全に崩れた。残るは、「研究科委員会(院教授会)で定年不延長を決定した」という壁だと思う。裁判官たちが、研究科委員会の「決定」に目を向けていることは確かで、研究科委員会の「決定」に正当性がないことが立証しなければならない。研究科委員会、専攻4人の「決定」に正当性がないことを堂々と主張すべきだ。その場合、保護されるべき権利を明確にすることが必要だ。ひと言でいえば、定年延長の「期待権」(一年更新の非正規雇用の裁判では権利とした確立している)を主張する。浅野先生の場合、解雇とか雇止めというのは当たらない。
同大では「大学院教授」は自己都合でなければ全員70歳まで定年延長されている。それは制度になっている。おそらくこの点は裁判官にも理解してもらえたと思う。少なくとも社会学研究科(2005年までは文学研究科)では69歳までに定年不延長になった人はいない。そうした中、「大学院教授」の先生が定年延長の期待権を持っていることは当然法的に認められる。そうした先生に対し、相応の理由がなければ、定年不延長の決定を行うことに正当性はありえない。それは、15年も20年も契約を繰り返してずっと働かせてきた非正規を、相応の理由がないのに契約を打ち切るのに正当性がないのと同じだ。そこで、定年不延長の「決定」が専攻4人の会議や研究科委員会で行われたことに正当性があるかどうかも問題になると思う。加えて、専攻4人の「審議結果」なるものは、同僚の集団的ハラスメント、名誉棄損の可能性が高いとなれば、各「決定」の正当性が認められない可能性は小さくない。
「浅野不良教授論」の批判は不可欠であるし、また裁判所に理解してもらうのも可能である。先生の陳述書においてかなり触れられているし、メディア学科の現役学生を含む教え子の方々の陳述書も有効であることは確かだ。その上での話だ。「大学院教授」として採用され、20年も何の落ち度もなく、後期と前期の多くの院生の指導に当たってきたのに、本学では「大学院教授」が全員70歳まで定年延長される中、先生には法的に保護されるべき定年延長の期待権があるとともに、研究科委員会等がその先生の定年不延長を「決定」したことは期待権の侵害であり、何ら正当性と合理的理由がないことをきちっと主張しておく必要があるのではないか。 〕
この裁判は提訴から2年4カ月がたちました。民事裁判は2年以内に判決を出すのが原則です。裁判の遅延は解雇された労働者にとって、一日一日が不利になります。
裁判所が、近畿において、長い歴史を誇り、権力機構の一翼を担う名門、学校法人同志社を叱責できるかどうかにかかってきていると思われます。裁判所が「大学の自治」「裁量」に逃げ込まないように、浅野教授に対する渡辺グループらの攻撃の異常性を徹底的に暴き、定年不延長の手続きの瑕疵・不正義を証明する必要があります。特に冨田氏の尋問で、彼の行ったことを明らかにして、彼の浅野不良教授論を粉砕することが求められています。偽証罪があります。冨田氏はウソをつけません。支援者で傍聴席を埋めて、冨田氏を監視しましょう。
被告側に、査読論文ないなどの非難で求釈明を要求
原告側が出した準備書面(11)は5月23日付で、〈査読論文の数を問題にすることが失当であること〉と題して、被告が1994年に通信社記者時代の著書を評価して大学院教授として採用したにもかかわらず、〈査読により本学外の学会で認められた論文は1本もない。」と主張し、原告の大学院教授としての適格性を否定していることに関し、「法学などの学問分野では、学会が研究者に発表や提案者になるよう依頼し、その発表文を学会の発行物に論文として掲載した場合も査読論文とみなされる。このような査読の定義及び目的からして、査読を経た論文の数が評価の対象とされるのは、主に大学が教員に教授などの職位を与えるかどうかを判断する際である」と反論して、こう述べています。
〈共同通信記者を22年間務めた原告は、被告から当初から大学院教授として採用されたものである。そうすると、査読を受けた論文の数は研究業績の評価において決定的な意味を持たず、原告について査読論文の数を問題にすることは失当である。
むしろ、文部科学省の教員組織審査において用いられている認定基準をもって資質を判断する方が適正かつ明確である。すなわち、原告は、1988年に、文部省(当時)から、大学院の博士後期課程における講義や博士論文の研究指導及び博士論文審査おいて主査を務めることのできる資質があると認められ、Dマル合の認定を受けているのであり、研究業績において原告の大学教授としての適格性は優に認められると言うべきである。
なお、原告は国際コミュニケーション学会(ICA)、国際オンブズマン学会、日本刑法学会、犯罪社会学会、犯罪と非行に関する全国協議会(JCCD)、日本平和学会で学会に招聘されて研究発表などを行い、その発表論文(英語を含む)がそれぞれの学会において公刊されている〉
この後、被告に対する求釈明として、同志社大学大学院社会学研究科メディア学専攻の博士課程(前期・後期)に在籍する大学院生に関し、2012年度から2016年度までの、入学試験の受験者数、合格者数、入学者(在籍)数と、その際、外国人留学生の人数、博士後期課程の院生の研究テーマも明らかにするよう求めました。
また、2014年6月の社会学研究科委員会において、同年3月31日をもって単位取得満期退学とするという超法規的決定を行ったナジ・イムティハニさん(インドネシアからの国費留学生)について次のような求釈明を行いました。
〈ナジさんの課程博士論文のメディア学専攻への提出期限は本年10月であるが、同氏の論文指導を行っている教員は誰か明らかにされたい。また、満期退学決定の際、2013年度の同氏の「指導所見」(社会学研究科事務室に保管されている後期学生の唯一の成績簿)を書いた教員は誰か明らかにされたい。原告が定年延長拒否された2014年3月31日以降、同氏の退学や論文指導について被告側、メディア学専攻教務主任から、それまで同氏の指導を担当してきた原告には一切連絡がない。
メディア学専攻の規定では、博士後期課程を満期退学した学生は退学から3年以内に博士論文の審査を受け、審査に合格すれば博士号(メディア学)を大学から取得できることができること、また、当該学生の博士論文の指導は退学時における指導教授(同氏の場合は原告)が行うことになっているが、被告側から原告には何の連絡もない。同氏の論文指導を誰が責任を持って進めているか明らかにされたい〉
また、原告が1994年4月の大学院教授就任以降、2013年10月25日の自称「臨時専攻会議」(自称「臨時議長」は小黒純教授)までの間に、原告の勤務態度、職務上の行状などに関し、被告(学校法人同志社)あるいは同志社大学大学院社会学研究科メディア学専攻、社会学部メディア学科、あるいは同研究科、学部ないし大学執行部から、忠告、注意、警告、その他の処分を行ったことがあるか、ある場合にはその日時、内容及び理由を明らかにするよう求めました。
人民と共に勝利まで闘う―原告・浅野教授のメッセージ
浅野教授は裁判の今後について次のように話しています。
〔 6月7日の期日で、裁判所が、証人について、冨田氏と私しか認めなかったのは、よく考えると、定年延長制度の諸問題、私のケースの異常性は、書面で勝負がついている=原告が完全に論破した=ので、庄司先生の人証までは必要ないという判断だったと思います。
今後は、「研究科委員会」(教授会)で浅野・定年不延長を議決しているという一つの壁を、裁判所がどう見るかです。大学の自治、教授会自治、大学の裁量の範囲内という判断があるのかもしれません。
被告側は怪文書の4人の反対を根拠に、「専攻会議」で私の定年延長を拒否したと言っていますが、4人は密室の審議結果を専攻会議で討議できなかったのです。理由もないからです。クーデターだったので、法的整合性は最初からありません。従って、小黒氏は4人の審議結果を私に通知し、大学院メディア学専攻教務主任(学長の任命)でもある私に「審議結果」を文書で渡し、それを研究科長の冨田氏に提出するように文書で依頼してきたのです。4人はいまだに「専攻会議で決まった」とは言えていません。社会学研究科の規定で、専攻会議の議長と、議案提案権を専攻教務主任である私が独占していたのもネックでした。4人は「専攻会議で決まった」「専攻で決まった」とは言えないのに、冨田氏や被告代理人はそう言い張っているのです。そこに最大の矛盾、瑕疵があります。対冨田氏裁判(神戸地裁)、5人裁判(京都地裁)、人報連会員のSさん裁判(編入試験問題)では、小國代理人は、「専攻や研究科で定年延長の可否は決まらない、すべて理事会が決めている」と主張しています。
被告側は本裁判の当初、「理事会できちんと審議している。定年延長対象者に「出講案内」と時間割表を送付することとが対象者の意思確認で、何も言ってこない場合は定年延長を希望しているということで、雇用契約をしている」という主張でした。そんなことは、いま、被告は言っていません。原告側の追及と、それを裁判所が指示したため、変わらざるを得なかったのです。いま、被告側は、13年12月9日に村田学長らが組合に表明したように、「定年延長は研究科で審議すべき事項で、大学執行部(学校法人同志社も)は一切関与しない」という見解です。「各研究科で定年延長の可否を決めている、専攻に分かれている研究科では、専攻(専攻会議)で決めて、延長が決まった院教授の担当科目と氏名が理事会にあがる」と主張しています。従って、専攻、研究科で否決された院教授は「学校法人同志社にとって必要かどうか」の審査を受けることはないのです。これは今年になって被告側の出した書証を見れば明らかです。したがって、「専攻」決定があったか、研究科員会の手続きは適切かが焦点になります。
13年10月30日午後の研究科委員会で、冨田議長はまず、渡辺氏については、従来通り一覧表(渡辺氏の担当科目を4人は全く決めておらず、冨田氏が研究科委員会の直前に勝手に記入)の5人の1人として実質的な審議なしに承認し、私はその後に、「専攻では拒否されたが、浅野先生が定年延長を希望しているから議題にする」と、私だけ、別枠の提案をしたのです。そこで、当事者の私が退席した後、4人は例の怪文書を配布。その後、継続審議となった11月13日の研究科委員会で、冨田氏が私を含めて委員会に諮らず、「独断」で新任教員、昇任人事と同じ、3分の2を可決条件とすると宣言して、無記名投票を強行したのです。
定年延長は、退職後の再雇用ではなく、単なる「延長」で、そこで、業績、勤務態度を問題にすることはあり得ないことです。同志社大学で定年延長制度ができた1951年以降、研究会委員会で定年不延長を投票で決めたのは初めてのことです。これは被告も認めています。
私の陳述書にそれらのことは書いています。私は、9・27の尋問でも、冨田氏を追及します。専攻の4人と冨田氏(村田学長も共謀していることが野村氏の陳述書で明らかに)が渡辺氏の指示で、このクーデター・暗黒裁判を、弁護士と周到に相談して進めたのです。社会学専攻の板垣竜太教授は私の定年延長の「審議未了」を心配し、投票での否決は想定していませんでした。投票までやったのは、弁護士らと相談して進めたのでしょう。この点、13年11月6日午前10時に矢内真理子氏が渓水館3階の社会学部パソコンルームで見た佐伯教授の残したパソコン画面で、小黒氏が「この3連休(11月初旬)の間にも、弁護士さんに忙しく動いてもらっている」というメールを佐伯教授に送っていることから明らかです。
矢内氏が13年11月6日に、私と「浅野先生を守る会」関係者にメールで報告したメモには、〈3件が小黒氏純氏からのメール。6日9時53分、小黒氏から「それは心を痛められたんですね…」(未読)というメールの後に、「この3連休(11月初旬)の間にも、弁護士さんに忙しく動いてもらっています」とあった。たぶん佐伯教授がこのPCで作業したのは11月5日の夜と思われる。浅野先生からの教務主任としての連絡(11月3日)も表示されていた。既読。推測するに、表示されていた50件は少なくとも11月6日~3日のメールであると思われる〉と書いてありました。
ここで小黒氏が言及した「弁護士さん」は、今回の法人側の代理人の弁護士ではなく、10・30配布文書に関して、私が刑法・民法上の問題があると通知したことで相談した別の弁護士と思われる。渡辺武達教授の代理人、池上哲郎の可能性もある。
この弁護士は俵法律事務所の小國弁護士らであることは間違いないでしょう。4人は弁護士と相談しながら同僚である私の追放をたくらんでいたのです。これが、良心教育を謳う大学の「自治」に当たるはずがありません。
冨田氏は13年11月13日夜、私が指導する院生、支援者ら10数名との団交で、「裁判を覚悟している」と数回述べています。最初から、裁判になることを承知で、暴挙を主導していたのです。これでは、研究科・学部の自治にはなりません。
裁判の今後は、裁判所が、4人の審議結果と研究科委員会決定の不当性を認めてくれるかどうかにかかってきました。これだけは、裁判官たちの「心証」で決まりますので、どうしようもありません。しかし、仮に負けても、高裁、最高裁で、これまでの闘いの上に、しっかりと闘えば、最終的には絶対に勝てると思っています。これほどの不条理、不正義はないと、私自身は思っています。それでも、司法の場で負ければ、それはそれで仕方がありません。裁判はあくまでツールであり、社会を変革するのは人民です。それが私のプリンシプルです。
9・27へ向けて、7月7日(木)午後6時半から9時まで、良心館で、外国人ジャーナリスト2人を招いて、浅野自主ゼミ主催の公開シンポを開きます。
9・27は傍聴席を、大学の真の自治と同志社新聞学の再興を求める同志で埋めてほしいと思います。
これからもどうぞよろしくお願いします。 〕
浅野教授の地位確認裁判はいよいよ大詰めです。
キシャクラブメディアは浅野教授の雇用闘争を無視していますが、人民の力で、社会化し、浅野教授を追放した同志社大学教職員の責任を追及していきましょう。「大学の自治」「研究科・学部・専攻の自治」に介入できないという理屈で、浅野教授の闘いを支援しない「左翼・リベラル」学者の責任も看過できません。浅野教授と浅野健一研究室の「自治」もまた重要だからです。
9月27日(火)午後1時半、京都地方裁判所208号法廷に結集しましょう。
(了)