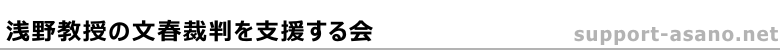恩師 白井厚慶應義塾大学名誉教授講演「学徒出陣と大学」の記録(浅野健一からの報告)
第二部 浅野教授定年延長拒否問題で緊急討論
【以下は白井厚慶應義塾大学名誉教授の「学徒出陣と大学」をテーマにした講演後に開かれた、浅野健一教授の「定年延長拒否問題」に関する緊急集会の記録である。この他に森類臣さん、小原健司弁護士、須賀達也さん、浅野教授の発言があった。】
●白井厚・慶應義塾大学名誉教授:
現代の社会を見ますと、いくつか大きい問題があるのですが、その一つは少子高齢化社会が急速に進んでいることだというのはみなさんよくご存知だと思います。
では、高齢化社会を乗り切るためにはどうすればいいか。日本の場合には特に急速で、よく出される例としましては、今は働く人4人で1人の高齢者を支えているが、そのうち3人で支えることになる。これを騎馬戦型というのですけれども、そのうち1人が1人を支える、これは肩車型。これは大変なことになってしまう訳ですね。
たとえば、高齢者というのはいろいろお金がかかりますから、それを若い人たちの稼ぎによって支えるということが、もう計算上出来なくなってしまうことが起こるんです。それをどう防ぐかどいうと、いろいろとありますが、簡単に言えば労働力をどんどん増やすことです。
これからは少子高齢化社会ですから、人口はどんどん減りますね。そして労働力が減る、つまり働いて税金を払って高齢化社会の福祉を支えるような人間が減るんですよ。働く人を減らさないためには、ひとつは女性を多用するということですね。出来るだけ多くの女性に働いてもらう。それから、もうひとつは高齢者で、元気な人はいつまでも働けるようにすることです。さしあたりはそのためにはみなさんよくご承知の様に、これまでは60歳が普通だったのですが、それではとてもダメだ。65歳まで、さらには70歳までも元気な人は働いてもらったらいいじゃないかということです。
アメリカでは、定年制というのは憲法違反です。定年は解雇と同じ労働権の切断で、年齢による格差を生みます。それじゃなくて、働ける人は出来るだけ働いてもらうのが当然ではないか。もちろん、その場合には、若い人に比べると多少能力が落ちれば給料が多少下がるかもしれない。そのかわり仕事量は少なくてもよいというようなことを工夫する必要があるでしょう。
その面からすると、我々教員は65歳で定年というのが普通になってきました。つまり、若い頃は経験不足であまり良い仕事ができなかったけれども、年を取ってからは、まだ元気で若いものに負けない良い仕事が出来るという人が多いわけです。まあ浅野君なんかはそういう人の典型なのだろうと思っておりまして、そういう人が少しでも長く働いて社会に貢献し、多少給料が減っても、生産者として税金を払い続けて、高齢化社会を支えてもらうのがいいだろうというのが、私が言いたい一つです。
もうひとつ、別の面で申しますと、今日ここで皆さんに大学の話を致しましたけれども、大学における人事はどのようにあるべきかという根本的な問題になります。ドイツ古典哲学の教えるところによりますと、大学の教授というのは全面的な自由を持ってなければならないということです。それから教授の身分というのは、普通の勤労者のように簡単に首を切ってはいけないということ。それは自由な発言をすることによって、優れた教授の優れた研究が生まれるからです。そのために教授の雇用については万全の配慮をして、出来るだけその教授が自由な発言をするのを認めながら、さらにいっそう真理を発見して社会のために貢献していって欲しい、ということだと思います。
広く見ますと、今回の事件は、よく分かりませんけれども、そんな二つの面、高齢化社会の維持という面と、教授の人権、学問の自由確保という面との、両面で考えて判断されるといいかな、という風に思っております。以上です。
●ある同志社大学の現職教授:
私は本学のある学部に所属しております一教員です。浅野先生のこれまでの研究活動、あるいは教育活動を脇から見てきました。非常に熱心に、研究にも教育活動にも当たられており、またこの社会のいろいろな不正や矛盾などの問題点を、特に被害者の立場から、あるいは声なき声の人の立場に立って問題点を追及してこられている、と感じてきました。私は浅野先生がこの同志社大学に来てくださって、素晴らしい活動を実践してこられたことに非常に感謝もしてきておりました。
しかし、急にこういうことになりまして、私もたいへん驚いております。同志社大学というところは、「言論の自由」、あるいは「思想の自由」を大切にしてきましたし、特に建学のいきさつを、いわゆる官学、官立の大学が持ち得ない私学の志を思い起こしてみる必要があると思います。創設者・新島襄らが「日本社会をこのように変えていきたい。そのためにはキリスト教の精神を基に、官の意向にとらわれないで教育・研究活動を行いたい」ということで作られた大学でしたし、そういう伝統を維持して来たと思います。
そういう中で、今回のように、体制派に対してかなり批判的な活動をされてきた先生を排除するかのようなことが行われたというのは非常に残念でありますし、建学の精神に反するのではないかと私は感じております。
私も詳しいことはあまりよく知らないのですけれども、実は今回の浅野先生の事例の前に、ビジネス研究科の先生が、この先生も非常に優秀な方なのですけれども、去年突然延長を認められないということがありました。この例にもとても驚いたわけですけれども、こういったことが繰り返されないようにと願っておりますし、またお二方の先生方の地位が保全されて回復されること、そして名誉も回復されることを祈っております。以上です。
●講演会後に届いた学生の感想
私と同世代の若者が、どんな思いで戦地へ赴いたのかを考えると、胸が痛くなりました。青春を踏みにじられてしまった悔しさや怒り、「天皇のため」「お国のため」「愛する人を守るため」決意を持って行くも、餓死してしまうという皮肉など、戦争からは残酷さばかり感じます。そして、戦争に行かざるを得なかった大学生に関する資料が少ないばかりか、大学はその生死さえないがしろにしている現実に不満を覚えました。多くの犠牲者を生んだであろう「学徒出陣」を忘れないために、大学生一人ひとりの生きざまを後世に残すために、大学側には原因追究と検証が求められます。
戦争になったら自国のために戦うかという統計で、日本は最下位だそうです。現在の日本の若者には、「戦争はいけない」という考えが当たり前になっています。若者には「天皇のため」「お国のため」戦うという感覚はないため、戦争を経験した世代や政府が「日本が戦争をしたのがいけなかったのだ」ということを肯定できないでいる限り、大義を持って戦ったであろう人たちと若者とのギャップは埋まらないのではないでしょうか。平和への思いが強い日本において、戦争の総括のつけ方が、世代をつなぐ鍵になると思います。【13年度2年浅野ゼミ学生】
--------------------------------------------------------------------
【参考1】
白井先生は2014年10月24日の浅野へのメールで、「アメリカでは1967年に雇用における年齢差別禁止法があり、欧州連合(EU) 指令でも 「雇用における均等処遇」 がある」と教えてくれた。超高齢化社会に向かう日本で、高齢者、女性、外国人の雇用を拡大することがますます必要になっている。
以下は、白井厚先生講演会に向けて、浅野がゼミ生、支援者に送った案内メールからの引用である。
《私は現在65歳です。私は1994年、22年間勤めた共同通信を退社し、同志社大学大学院社会学研究科メディア学専攻と社会学部メディア学科の教授に転身し、19年9カ月、ジャーナリズム論を教えてきました。他の大学にはないユニークな制度ですが、同志社大学では大学院で「法人同志社が必要とする院教員」だけに66歳から70歳まで5年間、定年を延長する制度があります。1951年以来、65歳を迎えた院任用教授全員にほぼ自動的に認められてきました。
ところが、私の「2014年度の定年延長」を審議した、院メディア学専攻の同僚教授4人は、2013年10月25日に「浅野健一教授 研究科委員会(院教授会)に定年延長を提案しない」と決定。11月13日には社会学研究科委員会が私の「2014年度の定年延長」を投票での採決で否決し、14年3月末で退職を余儀なくされる状況に追い込まれたため、12月27日(金)午後、学校法人同志社(水谷誠理事長)を相手に、従業員地位保全等仮処分命令申立書を京都地方裁判所に提出しました。近く本訴も起こします。
仮処分申し立ての際、京都司法記者会で会見しました。報告文と今日3年ゼミの学生13人の大学への要請文を添付します。
あまりにも急な事実上の解雇攻撃です。私の下で博士論文を書いている院生が2人います。一人は14年度の日本学術振興会(学振)DC2特別研究員に内定し、東電福島原発事件報道がテーマ。もう一人はインドネシア政府奨学金で来ているガジャマダ大学の専任教員の院生(後期課程3年)で、「アチェ紛争とピースジャーナリズム」を研究しています。
白井先生の講演会のチラシ〈表)の下に、学生たちが講演会の後、私の定年延長問題でアピールすると書いています。ゼミのOB・OGも参加します。
NHK「八重の桜」は12月15日に終わりましたが、12月1日放送の「八重の桜」では、新島襄は死の直前、同志社においては、型にはまらない同志を育成せよ、意見の異なることが大事である、いかなる理由でも学生を追放してはならない、と言い残したというシーンがオンエアされました。私を取り巻く人たちには、新島襄の遺訓が生かされていないと言わざるを得ません。なぜ私を同志社から追放するのか。NHKドラマが描く草創期の同志社と、現在の同志社大学の落差はあまりのも大きいと指摘します。
私の「定年延長なし」に疑問を持たれる方は学長へ要望書などを送ってください。
〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入 同志社大学 学長 村田晃嗣様
TEL: 075-251-3110 FAX:075-251-3075 E-mail:ji-shomu@mail.doshisha.ac.jp
大学のHPから「学長へのご質問・ご提言」もできます。http://www.doshisha.ac.jp/
みなさんのご支援をお願いします。
【参考2】以下は、浅野が白井ゼミ誌・2014年『創世』42号(14年11月発行)の特集《日本の「近代化」「民主化」の再考》へ寄稿した論稿である。
日本の民主化拒む大学とメディア――体験的大学論(1972年卒 浅野健一)
2千万人を超えるアジア太平洋の無辜の市民と日本の3百万国民を死に至らしめた大日本帝国による『大東亜戦争』の後、米軍占領下で新制大学が発足した。共同通信で22年間記者をした後、19994年から20年間、大学院教授を務めた同志社大学社会学研究科メディア学専攻博士課程の教育概要『メディアを通じて現代社会に迫る』は次のように説明されている。
[新聞学専攻は、戦前の軍国主義化と戦争を阻止できなかった要因のひとつをジャーナリズムの貧困に求め、民主主義の発展に向けたコミュニケーション状況の向上を目指して、1948年4月新制大学の発足とともに誕生した。]
メディア学専攻(旧・新聞学専攻)には和田洋一、城戸又一、鶴見俊輔各氏らリベラルな教員を擁していた。同志社大学には田畑忍学長(9月20日に亡くなった土井たか子さんは門下生)ら非戦・平和、人権を重視する研究者が多く、在日朝鮮人の指紋押捺問題などで教員たちが行政機関の前で座り込みをすることもあった。国家機密法案、昭和天皇の死去後の大嘗祭などで、学内で数百人の署名が集まり、教授会で反対決議が通ったと聞いた。私が赴任した20年半前には、学内にまだそんな反権力で自由な学風が感じられた。
現在の同志社大学はどうか。大学の顔である学長には、橋下徹氏(現大阪市長)と同じテレビ番組などに出演して有名になった村田晃嗣法学部教授がなっている。
村田氏は法学部教授時代の2003年には米英のイラク侵略・占領に自衛隊を派兵すべきと主張。安倍晋三政権が13年12月に強行成立させた特定秘密保護法にも賛成した。また、創価学会系の『第三文明』14年10月号で、14年7月の安倍晋三政権による集団的自衛権行使容認の閣議決定について、「(公明党との調整で)より丁寧なプロセス(経過)を踏むことができた」と述べ、「閣議決定で、日本が戦争できる国に変わってしまった」という批判を「ためにする議論」と決め付けている。
村田氏が教職員の投票で学長に選任されたのは13年1月だった。若手の職員が村田氏と対立候補の英文科教授との討論会を企画して、同志社の改革を雄弁に語った村田氏が僅差で選ばれた。「テレビに出ている人が偉い人」という軽いのりで選んだ教職員が多かったのだろう。
その後、13年4月には同志社大学の新キャンパスの敷地内に交番が設置された。地元自治会の「安心、安全な地域を」という声に押されて、無償で交番用地を提供したのだ。
それでも、学問・研究の自由を縛るおそれが強い特定秘密保護法が本格的に審議されていた13年9月から10月にかけて、私が所属する社会学部教授会(50人)で、何とか反対決議ができないかと考えていた。
特定秘密保護法案は、憲法21条「表現の自由」に「公益及び公の秩序」という条件をつけた自民党改憲草案の先取りであり、かつて中曽根政権などが画策・失敗したスパイ防止法・国家秘密法を復活させるものだからだ。
何とか自分の職場で声を上げようと思い、リベラル左翼系とされる若手の教員に相談したが、「学部で通すのは不可能だろう」ということだった。
そのころ、13年10月29日、私は大学院メディア学専攻の同僚4人によって、突然「2014年3月末解雇」を通告された。一種のクーデター、暗黒裁判だった。10月30日に4人が社会学研究科委員会(構成員35人)で配布した「浅野教授定年延長審議資料」には次のようなことが書いてあった。
・《「運動」としての活動はあっても、大学院の教授の水準を満たす研究はない》
・《大学院教授としての品位にかける表現 例「ペンとカメラを持った米国工作員」「労務屋」「企業メディア"用心棒"学者」「メディア企業御用学者」「デマ」など》
・《専攻科の各教員は常時強いストレスにさらされている。文書送付等が顕在化しているときは勿論、その後も長く続く恐怖感。これによる突発性難聴や帯状疱疹などの発症》
非科学的言い掛かりばかりだった。
同志社大学では65歳になった大学院教授に70歳まで定年を1年ずつ延長する制度があるが、私は文系学部では初めて定年延長を拒否された。20年間も院教授を務めた私を「教員失格」と非難した。
同研究科、学校法人同志社(水谷誠理事長)も「定年延長拒否」という形での不当解雇を強行し、14年3月末、教授のポストを奪われた。このため4月1日から全く教壇に立てなくなり、20期まで続いた13年度浅野ゼミ(3年生)も暴力的に解体された。これに対し、私は14年2月、京都地裁民事6部に「従業員地位確認等請求訴訟」を起こして、これまで3回の口頭弁論が開かれた。
私が解雇されそうになっていた13年11月、白井厚先生が村田学長宛に「浅野健一教授の業績評価について」と題した文書を出してくれた。 裁判については、「浅野教授の文春裁判を支援する会」のHPを参照してほしい。
同志社大学の変節を招いたのは、教職員の保守化とともに、学生自治の崩壊が原因と私は見ている。同志社大学には、全国の私学でも有数の学生運動の歴史がある。大学全体の自治会を学友会と呼んでおり、新左翼系のリーダー、藤本敏夫氏(故人、歌手の加藤登紀子さんの夫だった)、矢谷暢一郎米ニューヨーク州立大学教授らが委員長を務めた。伝統ある学友会は、私が在外研究で不在だった2003年に解散大会を開いて消滅した。解散大会を開けるぐらいなら、存続できるのではないかと思った。誰がどうやって学友会を解体したか、いまだに分からない。
学生自治会のない大学は授業料の値上げを続けた。リーマンショック後もスライド制で値上げして、全国の私大の中では比較的安かった授業料が早慶並みになった。
現在の大学では「産学協同」も当たり前で、企業の名前を掲げた冠講座が横行している。村田氏は読売新聞と組んで講座を続けているし、メディア学科関係では京都新聞系の組織から資金を受けた授業がある。大学ほど、既得権益にこだわるところもない。また、非正規雇用をいち早く始め、人件費の削減に必死だ。
私は大学での最後のゼミ企画として、14年1月6日、白井先生の講演会を同志社で最も大きいホールで開催した。白井先生は「学徒出陣」をテーマにして、学問の在り方、知識人の責任について学生たちに語ってくれた。1年生の参加者は、先生の「学問は批判から始まる。しかし今の学者は政府に従うだけだ。なぜ大学は今の政治を疑わないのか」「戦争の直接の原因は軍部だが、高学歴の者が思考停止したから戦争が起きた」という言葉が強く印象に残ったと言っている。
講演後に開かれた私の「定年延長」に関する集会で、次のように発言してくれた。
[少子高齢化社会を乗り切るためには、女性を多用するということと、高齢者で、元気な人はいつまでも働けるようにすることです。米国では定年制というのは憲法違反です。また、ドイツ古典哲学の教えるところによりますと、大学の教授というのは全面的な自由を持ってなければならないということです。それは自由な発言をすることによって、優れた教授の優れた研究が生まれることです。そのために教授の雇用については万全の配慮をして、出来るだけその教授が自由な発言をするのを認めながら、さらにいっそう真理を発見して社会のために貢献していって欲しい、ということだと思います。]
白井先生の大学改革への提言から学びたい。
以上